モーツァルト(1756-1791)
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」ハイライツ
ドン・ジョヴァンニ: バリエル・バキエ
ドンナ・アンナ: ジョアン・サザーランド
ドンナ・エルヴィーラ: P. ローレンガー
ドン・オッターヴィオ: ヴェルナー・クレン
レポレッロ: ドナルド・グラム
ツェルリーナ: マリリン・ホーン
マゼット: レオナルド・モンレアーレ
騎士長: クリフォード・グラント
アンブロジアン・シンガーズ
イギリス室内管弦楽団
指揮: リチャード・ボニング
録音: 1968年
(74:41)
今夜はモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」です。
「ドン・ジョヴァンニ」もブログでは3回目の登場となりますが、この演奏はいくぶん異色なものと言えるかもしれません。たとえば、ツェルリーナにマリリン・ホーンを擁するなど、偉大な歌手の饗宴を愉しむといった趣です。
アリアに所々に装飾音を施すなど、モーツァルトという素材を用いた一種のベルカント・オペラとなっていますが、それでも充分に愉しめるのは、やはり歌手陣のすばらしさに因るところが大きいのでしょう。殊に第1幕のフィナーレのアンサンブルなどは聞きものです。
なお、チェンバロによる即興の通奏低音は、劇的効果を高めるのではなく、長閑さを醸し出しています。序曲では間が抜けている感も無きにしも非ずですが(汗)。(第2幕のドン・ジョヴァンニによるアリアの伴奏となるマンドリンも不思議な音です(汗)。)
ところで、「ドン・ジョヴァンニ」の場合、ドラマの流れを損なわずに名場面をCD一枚に収めるのは難しいですね。"このハイライツ盤ではこれが入っているけれど、こちらでは入っていない"といったことがありますから。
それでも、CD3枚分の全曲を腰をすえて聞くとなると、時間の問題もさることながら、なかなかその気力も湧いてこないのは、この蒸し暑さゆえのことでしょうか。
.
2009/Aug
23
Sunday
19:00
Comment(-)
ヤナーチェク(1854-1928)
歌劇「ブロウチェク氏の旅」より
第2部「ブロウチェク氏の15世紀への旅」
マチェイ・ブロウチェク: ヤン・ヴァツィーク
ヴュルフル/市参事会員: ズデニェク・プレフ
詩人スヴァトプルク・チェフ(原作者)/
第2のターボル兵: イワン・クスニエル
ドムシーク: ロマン・ヤナール
ケドルタ: レンカ・シュミードヴァー
クンカ: マリア・ハーン
ヴァツェク: ヴァーツラフ・シベラ
ミロスフラフ: アレシュ・ブリスツェイン
ヴォイタ: ヤロスラフ・ブジェジナ
大学生: マルチナ・バウエロヴァー
ペツシーク: ペテル・ストラカ
第1のターボル兵: チャールズ・ギップス
BBCシンガーズ
合唱指揮: スティーヴン・ベターリッジ
BBC交響楽団
指揮: イジー・ビエロフラーヴェク
録音: 2007年
(57:58)
今夜はヤナーチェクの「ブロウチェク氏の旅」第2部です。
第1部の「月への旅」は、先月3日のヤナーチェクの生誕日に聞き、このオペラのことにも少し触れています。
深夜便56 「ブロウチェク氏の旅」第1部 ビエロフラーヴェク
今夜は後半の第2部「15世紀への旅」となりますが、またしても酔っぱらったブロウチェク氏が夢の中で、今度は15世紀のフス戦争に巻き込まれてしまうという筋書きです。
敵のスパイと勘違いされ、火あぶりの刑に処される直前で酔いから醒めて現実に戻るという、これまた第1部に続くコミック・オペラですが、ヤナーチェク特有の筆致に彩られたオペラです。
スメタナ、ドヴォルザーク、そしてヤナーチェクといったチェコ&モラヴィアの作曲家のオペラが、イタリアやドイツ、オーストリーの作曲家作品ほど演奏されないのは、作品そのものの問題というより、原語の問題が第一に挙げられるでしょう。
スメタナの「売られた花嫁」の録音などは、オリジナルよりも英語やドイツ語版の方が多いかもしれません。ヤナーチェクのオペラは、サー・チャールズ・マッケラスの功績によってだいぶ知名度が上りましたが、欲は言いませんので、英語でもドイツ語でももっと聞く機会ができればと思います。
なお、今日8月12日は、ヤナーチェクの命日にあたります。
2009/Aug
12
Wednesday
00:00
Comment(-)
ショスタコーヴィチ(1906-1975)
歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」全曲
1932年原典版
ボリス: オーゲ・ハウグランド
ジノーヴィー: フィリップ・ラングリッジ
カテリーナ: マリア・ユーイング
セルゲイ: セルゲイ・ラーリン
アクシーニャ: クリスティーネ・チーシンスキ
ボロを着た農民: ハインツ・ツェドニック
老囚: クルト・モル
パリ・バスティーユ歌劇場管弦楽団&合唱団
合唱指揮: グンター・ワーグナー
指揮: チョン・ミュンフン
録音: 1992年
(79:20/76:27)
今夜はショスタコーヴィチの「ムツェンスク郡のマクベス夫人」です。
このオペラは1930年から32年にかけて作曲されていますので、ショスタコーヴィチ20代半ばの作品となります。性的描写など過激な内容名であるにもかかわらず、1934年の初演から好評を博しました。ところが、ソ連の独裁者スターリンの逆鱗に触れ、ショスタコーヴィチは窮地に追い込まれてしまいます。
これが旧ソ連の音楽史上、悪名高い「プラウダ批判」ですが、この批判は"粛清"を暗示するものとして、ショスタコーヴィチは生命の危機に晒されることになったのです。これ以来、紆余曲折はあったにせよ、生涯を通じてショスタコーヴィチが悩まされることになります。
ソビエト連邦は1922年に成立、1991年に崩壊していますから、その歴史はおよそ70年。この期間に6,200万以上が粛清されたと現ロシア政府が公開していますが、まさにその中に生きたショスタコーヴィチは、容易に想像し難い苦難の連続であったと思われます。
「マクベス夫人」はまだそのような恐怖がショスタコーヴィチを襲う前に書かれたオペラではありますが、それを暗示するような筆致となっていることは、この作曲家を読み解く一つの鍵となっているような気もします。どのような状況下であれ、この鬱屈した趣は、やはりショスタコーヴィチはショスタコーヴィチであるしかなかったのかもしれません。
なお、このオペラのヒロイン名はカテリーナ・イズマイロヴァですが、殺人に手を染め、野心を抱いた女性として、シェイクスピアの「マクベス夫人」の名を比喩として用いられたようです。(「ムツェンスク郡のマクベス夫人」の原作はニコライ・レスコフによる小説。)
今日8月9日はレオンカヴァルロの命日でもありますが、今夜はショスタコーヴィチの命日を優先しました。
.
2009/Aug
09
Sunday
00:00
Comment(-)
ヴェルディ(1813-1901)
歌劇「マクベス」全曲
マクベス: ピエロ・カプッチッリ
バンクフォー: ニコライ・ギャウロフ
マクベス夫人: シャーリー・ヴァーレット
侍女: ステファニア・マラグ
マクダフ: プラシド・ドミンゴ
マルコム: アントニオ・サヴァスターノ
医師: カルロ・ザルドー
従者: ジョヴァンニ・フォイアーニ
刺客: アルフレード・マリオッティ
伝令: セルジオ・フォンタナ
3人の幻影: アルフレード・ジャコモッティ、マリア・ファウスタ・ガラミーニ、マッシモ・ボルトロッティ
ミラノ・スカラ座管弦楽団&合唱団
合唱指揮: ロマーノ・ガンドルフィ
指揮: クラウディオ・アバド
録音: 1976年
(79:53/74:00)
今夜はヴェルディの「マクベス」です。
「マクベス」は生涯に26のオペラを遺したヴェルディの10作目にあたり、1846年から47年にかけて作曲されています。3作目の「ナブッコ」を除けば、ヴェルディの作品でことに親しみがあるオペラとなると16作目の「リゴレット」(1851年初演)以降となるでしょう。
しかし、「マクベス」は作曲家30代の作品とは思えないほど神経が行き届いた完成度を誇る作品と思います。ヴェルディはその出来映えにかなり自信をもっていたようですが、「マクベス」は長い間、ヴェルディの故国イタリアでも演奏されることが稀であったようです。
そのような不遇の時代でも演奏されていた国がドイツということは興味深いことです。「マクベス」は華麗なアリアを堪能するといった趣("情")ではなく、"知"と"意"に比重が偏っているため、そのようなことがあったのでしょう。
いくぶん"理詰め"の感があることは否めませんが、後年ライバルであったワーグナー作品に対抗する自作として「マクベス」を挙げていることには頷けます。聞いて"楽しい"オペラではないかもしれませんが、"心理劇"として聞けばその完成度はヴェルディの中期&後期作品に勝るとも劣らない魅力があることでしょう。
.
2009/Aug
07
Friday
21:00
Comment(-)
レオンカヴァルロ(1857-1919)
歌劇「道化師」全曲
カニオ: ユッシ・ビョルリンク
ネッダ: ヴィクトリア・デ・ロス・アンヘレス
トニオ: レナード・ワーレン
シルヴィオ: ロバート・メリル
ベッペ: ポール・フランケ
村人: ジョージ・チェハノフスキー /
リチャード・ライト
コロンバス少年合唱団
監督: ハーバート・ハフマン
ロバート・ショウ合唱団
合唱指揮: ロバート・ショウ
RCAヴィクター管弦楽団
指揮: レナート・チェルリーニ
録音: 1953年
(69:31)
今夜はレオンカヴァルロの「道化師」です。
前回は「カヴァレリア」をマスカーニの命日に聞きましたが、ヴェリズモ・オペラの両雄「道化師」の作曲家レオンカヴァルロの命日は1週間違いの8月9日となります。レオンカヴァルロは既にここでも2回登場していますので、今年のその日は別のオペラを聞く予定です。
さて、今夜聞いた「道化師」と前回の「カヴァレリア」では男声主役がともにビョルリンクとなっています。(CDジャケットもともにビョルリンクですね(^-^) 1960年に心臓発作でわずか49歳で生涯を閉じてしまったビョルリンクですが、芯がありながらしなやかな美声はここでも存分に堪能することができました。
意識していたわけではありませんが、なぜかイタリア・オペラに興味をもった頃に聞いていた録音にビョルリンクがキャストされている確率が高いことに気づきました。前回の「カヴァレリア」だけでなく、「イル・トロヴァトーレ」、そして「ラ・ボエーム」があります。
深夜便5 プッチーニ 「ラ・ボエーム」 ビーチャム
2009/Aug
05
Wednesday
19:00
Comment(-)
マスカーニ(1863-1945)
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」全曲
トゥリッドゥ: ユッシ・ビョルリンク
サントゥッツァ: レナータ・テバルディ
ルチア: リナ・コルシ
アルフィオ: エットレ・バスティアニーニ
ローラ: ルチア・ダーニ
フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団&合唱団
合唱指揮: アンドレア・モロシーニ
指揮: アルベルト・エレーデ
録音: 1957年
(73:10)
今夜はマスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」です。
このオペラはブログ2回目の登場となりますが、実は、前回エントリーした直後に思い違いがあることに気づきました(>_<)
深夜便36 「カヴァレリア・ルスティカーナ」 レヴァイン
そこでは、「イタリア歌劇を好きになるきっかけとなった曲であり、録音」と述べました。確かにイタリア歌劇が好きになって、そのレヴァイン盤は早い段階で聞いていますが、そのきっかけとなったのは、今夜聞いたエレーデ盤でした。
エレーデ盤の音楽の豊かさは比類がありません。ビョルリンク、テバルディ、バスティアニーニといった往年の名歌手、そしてオーケストラの豊潤なフレージングは、このオペラの悲劇性よりも「歌」でキャンバスを塗りつぶした感さえあります。
そこで、もう少し現代的な(?)レヴァイン盤を取り出すことが多かったのだと思いますが、やはり今あらためて聞きなおしてみると、エレーデ盤により"オペラ"としての魅力を感じました。歌もすばらしいですが、間奏曲の豊潤でありながら厭らしい節回しとなっていないことも特筆しておきます。
いかにも「旧き佳き時代」の産物といった趣もあるかもしれませんが、録音状態に古臭さは感じました。さすがはDECCA/LONDONといったところでしょうか。
なお、前述の思い違いをエントリー後すぐにでも訂正しようかと思いましたが、今日という日を待ちました。今日8月2日はマスカーニの命日にあたりますから。
.
2009/Aug
02
Sunday
21:00
Comment(-)
ワーグナー(1813-1883)
楽劇「ニーベルングの指環」
第2夜「ジークフリート」第3幕
さすらい人: テオ・アダム
エルダ: オルトルン・ヴェンケル
ジークフリート: ルネ・コロ
ブリュンヒルデ: ジャニーヌ・アルトマイアー
ドレスデン国立歌劇場管弦楽団
指揮: マレク・ヤノフスキ
録音: 1982年
(15:01/65:17)
今夜はワーグナーの「ジークフリート」第3幕です。
今月は「ジークフリート」を一幕ごとに聞いてきましたが、今回がその最後にあたります。
深夜便55 ワーグナー 「ジークフリート」第1幕 ヤノフスキ
深夜便61 ワーグナー 「ジークフリート」第2幕 ヤノフスキ
ワーグナーは1857年に第2幕までを作曲すると、いったん「ジークフリート」から離れ、「トリスタンとイゾルデ」、「ニュルンベルクのマイスタージンガー」といった名作を完成しています。ふたたび「ジークフリート」に戻って第3幕に着手したのは、10年以上も経た1869年のことでした。
この中断の事情にはさまざまなことがあったようですが、最大の問題は、「ニーベルングの指環」という大作を演奏する目処がたたなかったことがあるでしょう。しかし、その12年の空白の期間には経済的な問題を解消することが起きています。

1864年3月、ルートヴィヒ2世がバイエルン国王として戴冠、ワーグナーを招聘。放浪の身であったワーグナーは5月4日に王に謁見しています。時にルートヴィヒ2世は18歳、ワーグナーは50歳でした。
ルートヴィヒ2世は「トリスタンとイゾルデ」、「ニュルンベルクのマイスタージンガー」、「ニーベルングの指環」、「パルジファル」といった作品上演の援助をしたばかりではなく、王国内のバイロイトにワーグナー作品のみを上演することを目的とする劇場まで建てています。
ルートヴィヒ2世は1886年6月13日にシュタンベルク湖にて謎の水死を遂げてしまいますが、当時ミュンヘン大学に留学していた森鷗外はそれをもとに「うたたかたの記」を書いています。ワーグナー、鷗外といったことよりも、ルートヴィヒ2世はディズニーランドのシンデレラ城のモデルともなっているノイシュヴァンシュタインの城主として馴染みがあるかもしれませんね(^^)
ノイシュヴァンシュタイン城内は、ワーグナーのオペラ場面を再現したものに彩られているそうです。今夜は「ジークフリート」最終幕を聞きながら、夢見る王の現実逃避に浸ってみました(≧∇≦)
.
ヴィヴァルディ(1678-1741)
歌劇「オルランド・フリオーソ」ハイライツ
オルランド: マリリン・ホーン
アンジェリカ: V. デ・ロス・アンヘレス
アルチーナ: L. ヴァレンティーニ・テラーニ
ブラダマンテ: カルメン・ゴンザレス
メドロ: ラヨシュ・コスマ
ルッジェーロ: セスト・ブルスカンティーニ
アストルフォ: ニコラ・ザッカリア
コーロ・アミーチ・デラ・ポリフォニア
合唱指揮: ピエロ・カヴァッリーニ
イ・ソリスティ・ヴェネティ
指揮: クラウディオ・シモーネ
録音: 1977年
(72:43)
「四季」で圧倒的な知名度を誇るヴィヴァルディですが、「四季」が含まれる協奏曲集「和声と創意の試み」、「調和の霊感」や「グローリア」などを除くと、その他の作品はあまり親しみがないかもしれません。
このほかの作品も意外に(?)録音はあり、私もいくつかの協奏曲集などを聞いたことがありますが、その他の作品の知名度が高まらない理由は、あまりに多くの曲が遺されているというアイロニーが潜んでいるような気がします。
なにせ協奏曲だけで500曲以上、オペラも現存するだけで50以上という夥しい数の作品が遺されているのですから!
それでも、協奏曲とは異なり、オペラとなると多くの録音は無いようです。私が最初の興味をもったのは、シモーネ&イ・ソリスティ・ヴェネティによるオペラの序曲集でした。同コンビによる歌劇「オルランド・フリオーソ」があると知り、聞いてみましたが、バロック・オペラを存分に堪能できる名曲と思いました。
ヘンデルのオペラのように1曲のアリアが長大であり、歌手の技巧の見せ場がいたるところにあります。筋書きはそのヘンデルの「アルチーナ」に似ており、この2つのオペラでは、アルチーナ、ルッジェーロ、ブラダマンテと登場人物が同一となっています。
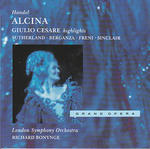
ヘンデル 歌劇「アルチーナ」
なお、昨日7月28日はヴィヴァルディの命日でした。
2009/Jul
29
Wednesday
22:00
Comment(-)
モーツァルト(1756-1791)
歌劇「後宮からの誘拐」KV384 全曲
コンスタンツェ: ロイス・マーシャル
ブロンデ: イルゼ・ホルヴェーク
ベルモンテ: レオポルド・シモノー
ペドリッロ: ゲルハルト・ウンガー
オスミン: ゴットロープ・フリック
パシャ・セリム: H. ラウラベンタール
ビーチャム・コーラル・ソサエティ
ロイヤル・フィルハーモニック管弦楽団
指揮: サー・トーマス・ビーチャム
録音: 1956年
(77:10/37:02)
今夜はモーツァルトの「後宮からの誘拐」です。
このオペラは1782年の作ですから、モーツァルト26歳、コンスタンツェ・ヴェーバーと結婚した年となります。なお、有名な話ではありますが、コンスタンツェはかのカルロ・マリア・フォン・ヴェーバーの従姉にあたります。このオペラのヒロインがコンスタンツェという名なのは偶然なのでしょうか?(^-^)
オペラ以外のジャンルですと、「後宮」が作曲された1782年には、交響曲第35番「ハフナー」、弦楽四重奏曲第14番「春」といった名作が生み出されています。「ハフナー」は後期6大交響曲の幕を開けるものであり、「春」は所謂「ハイドン・セット」の冒頭を飾る作品です。
弦楽四重奏曲では中期の力作、交響曲では後期の幕を開けた年でしたが、オペラではこの「後宮」によって中期を終えたということになるでしょうか。なお、ピアノ協奏曲はこの時点で第10番までしか書かれておらず、このジャンルはモーツァルト中後期にたて続けに名曲が生み出されることになります。
さて、「魔笛」を例外とすると、モーツァルトの高名なオペラはイタリア語の台詞によるものが多い感がありますが、「後宮」はドイツ語のリブレットに作曲されています。登場人物は語り役の太守セリムを含んでも6人と「コシ・ファン・トゥッテ」と同じく絞り込まれています。
それゆえでしょうか、録音でも脇役にいたるまで名歌手が起用されていることが嬉しい限りです。このビーチャム盤では、ヒロインのメイドにホルヴェーク、ヒロインの恋人役ベルモンテの召使ペドリッロにウンガーという豪華さ。そして、悪役の代名詞のようなオスミンにはフリック!
もちろん、マーシャルのコンスタンツェとベルモンテのシモノーも品のある美声を聞かせてくれます。1956年のステレオ録音ということもあり、さすがに古めかしいことは否めませんが、充分に「後宮」を聞く愉しさを満喫できました。
なお、2枚目のディスクには第3幕の後に、シモノーによるオペラ・アリアとコンサート・アリアが全5曲32分にわたって収められています。これまた輪郭がくっきりとした美声を聞かせてくれます。

