ムソルグスキー(1839-1881)
人民音楽劇「ボリス・ゴドゥノフ」全曲より
第2幕、第3幕第1場~第2場
1872年改訂オリジナル版
ボリス: アレクサンドル・ヴェデルニコフ
ニキーティチ: ヴラディミール・フィリッポフ
ミチューハ: ニコライ・ニヅィエンコ
シチェルカーロフ: アレキサンドル・ヴォロシロ
シュイスキイ: アンドレイ・ソコロフ
ピーメン: ヴラディミール・マトリン
偽グリゴーリイ: ヴァディスラフ・ピアフコ
居酒屋の女主人: リュドミラ・シモノーヴァ
ワルラーム: アルトゥール・エイゼン
ミサイール: アナトーリ・ミシュティン
ソヴィエト連邦TV・ラジオ大合唱団
合唱監督: クラヴディ・プティッツァ
合唱首席指揮: リュドミラ・エルマコーヴァ
スプリング・スタジオ児童合唱団
合唱監督: アレクサンドル・ポノマレフ
ソヴィエト連邦TV・ラジオ大交響楽団
指揮: ヴラディミール・フェドセーエフ
録音: 1978-1983年
(64:26)
今夜はムソルグスキーの「ボリス・ゴドゥノフ」です。
プロローグから第1幕までは、今年の3月に聞いていますが、今夜は第2幕と第3幕の第2場途中までです。なぜ中途半端かというと、これがCDの区切りになっているからです(≧∇≦)
深夜便13 ムソルグスキー 「ボリス・ゴドゥノフ」 フェドセーエフ
プロローグと第1幕は滾々と湧き出る素材の多様性もあって親しみやすい場面が多く、第2幕前半は交響曲での"スケルツォ"的な要素があり、「ボリス・ゴドゥノフ」特有の心理劇としての真骨頂はそれ以降となるでしょうか。
今回も前回に引き続きフェドセーエフ指揮による録音で聞いていますが、独唱陣の個性は際立っていないものの、第3幕の冒頭といい合唱の登場となると、抒情的な美しさが顕著となってきます。
リリカルなムソルグスキー、リリカルな「ボリス・ゴドゥノフ」というと違和感があるかもしれませんが、私はこの美しさがとても好きです。
ワーグナー(1813-1883)
歌劇「ローエングリン」第1幕
ローエングリン: ヴォルフガング・ヴィントガッセン
エルザ: エリナー・スティーバー
テルラムント: ヘルマン・ウーデ
オルトルート: アストリッド・ヴァルナイ
ハインリヒ国王: ヨーゼフ・グラインドル
王の伝令: ハンス・ブラウン
第1の貴族: ゲルハルト・シュトルツェ
第2の貴族: ヨゼフ・ヤンコー
第3の貴族: アルフォンス・ヘルヴィヒ
第4の貴族: テオ・アダム
バイロイト祝祭合唱団
合唱指揮: ヴィルヘルム・ピッツ
バイロイト祝祭管弦楽団
指揮: ヨーゼフ・カイルベルト
録音: 1953年
(65:50)
今夜はワーグナーの「ローエングリン」第1幕です。
戦後バイロイト音楽祭が再開されたのは1951年、その翌年から1956年までバイロイトで活躍しており、NAXOSの解説書によると以下の演目を担当しています。
1952-56: 「ニーベルングの指環」
1953-54: 「ローエングリン」
1954-55: 「タンホイザー」
1955-56: 「さまよえるオランダ人」
「タンホイザー」以外はすべて商用録音されていると思いますが、ことに長年にわたってお蔵入りとなっていた「指環」がTESTAMENTレーベルから近年復刻されたことは記憶に新しいところです。
この「指環」がリリースされるずっと前から、「ローエングリン」と「オランダ人」はそれぞれのエヴァー・グリーン的な存在として君臨としていた思われます。もとの録音はDECCAが収録したようですが、一時期からTELDECからリリースされていました。
その版権が切れたためでしょうか、「ローエングリン」はNAXOSから板起こしとしてリリースされています。温室のことはよく分かりませんが、CD4枚であったものが3枚に収まっており、聞きやすくなっています(^-^)
カイルベルトの指揮は堅実でありながら、朴訥すぎることなく全体の流れを鳥瞰したものと思います。そして、当時のピッツ率いる合唱団の素晴らしさも特筆すべきでしょう。
上記「オランダ人」でも主役として共演していたウーデとヴァルナイがここでも、悪のコンビとして名歌唱を聞かせてくれますし、ヴィントガッセンも好調、グラインドルはハズレがありません。
モノラル録音とはいえ、戦後バイロイトの黄金時代の一幕を記録したものとして貴重でしょう。
.
2009/Sep
18
Friday
21:00
Comment(-)
モーツァルト(1756-1791)
歌劇「フィガロの結婚」ハイライツ
伯爵夫人: キリ・テ・カナワ
スザンナ: ルチア・ポップ
ケルビーノ: フレデリカ・フォン・シュターデ
フィガロ: サミュエル・ラメイ
アルマヴィーヴァ伯爵: トーマス・アレン
バルトロ: クルト・モル
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮: サー・ゲオルグ・ショルティ
録音: 1981年
(62:38)
今夜はモーツァルトの「フィガロの結婚」です。
これまで聞いてきた同曲の最高水準の一つこそ、今夜聞いたショルティ指揮によるものと思います。デイム・キリとサー・トーマスによる伯爵夫人と伯爵、ポップのスザンナ、フリッカのケルビーノ、ラメイのフィガロと配役は豪華を極めています。
さらに、全く他を寄せつけない歌唱を聞かせるのは、モルのバルトロでしょう。このバス歌手特有の深みだけではなく、いかにモルが正確に軽みをもって早口で歌えるかを証明した録音でもあります。
また、ショルティというと先鋭な指揮ぶりがトレードマークのようになっていますが、ロンドン・フィルと組んだものは、淡いロマンティシズムが漂う柔和さが特徴となっていると思います。
この演奏は全曲盤を聞いてこそ魅力を満喫できるのですが、なぜか抜粋盤となると、あまり感銘を受けません。如何に全体としての見通しが良く、前後関係のツボが押さえられた演奏ということかもしれません。(これと同様のケースに、マッケラスの「コシ・ファン・トゥッテ」があります。)
.
ドヴォルザーク(1841-1904)
歌劇「いじっぱりな恋人どうし」全曲
ヴァヴラ: ロマン・ヤナル
トニク: ヤロスラフ・ブシェジナ
リホヴァ: ヤナ・シコロヴァー
レンカ: ズデーナ・クロウボヴァー
養父: グスタフ・ベラチェク
プラハ・フィルハーモニック合唱団
合唱指揮: ヤロスラフ・ブリッチ
プラハ・フィルハーモニア
指揮: イルジー・ビエロフラーヴェク
録音: 2003年
(76:18)
今夜はドヴォルザークの「いじっぱりな恋人どうし」です。
オーケストラ曲と室内楽曲で有名なドヴォルザークですが、10曲以上のオペラも遺しています。「いじっぱりな恋人どうし」は1881年に初演された4つ目のオペラとなり、コミック・オペラに属します。
原題の "Tvrdé palice" をどのように和訳すればよいのか分かりませんが、「頑固者たち」、「頑固な連中」といった訳もあるようです。英訳は "The Stubborn Lovers" ですので、「いじっぱりな恋人たち」が近いとは思うものの、ここではより一般的な「いじっぱりな恋人どうし」 としました。重訳となるでしょうけれども(≧∇≦)
このオペラの初演は1881年と前述しましたが、作曲そのものは1874年にさかのぼります。交響曲では第4番、弦楽四重奏曲では第7番が作曲された年と同じとなりますが、ドヴォルザークの名声が確立される作品群よりは前に書かれたオペラとなります。
「いじっぱりな恋人どうし」はコミック・オペラということもあるでしょうが、親しみやすい旋律に溢れた作品と思います。ドヴォルザークも気に入っていた曲であったのでしょう、このオペラの一部を後年、第8交響曲の第3楽章に転用しています。
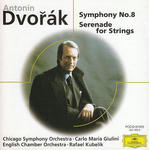
ドヴォルザーク 交響曲第8番
ジュリーニ指揮 シカゴ交響楽団
今日9月8日はR. シュトラウスの命日でもありますが、今年はドヴォルザークの誕生日を優先させました。
.
2009/Sep
08
Tuesday
21:10
Comment(-)
スメタナ(1824-1884)
歌劇「売られた花嫁」ハイライツ
マックス・カルベックによるドイツ語版
クルシーナ: バリー・マックダニエル
カーティンカ: ツヴェトカ・アフリン
マリー: メリッタ・ムーゼリー
ミーヒャ: マルッティ・タルヴェラ
アグネス: ルート・ヘッセ
ハンス: ルドルフ・ショック
ケツァール: クルト・ベーメ
ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団
合唱指揮: ワルター・ハーゲン・グロール
ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団
指揮: ハインリッヒ・ホルライザー
録音: 1963年ごろ
(49:32)
今夜はスメタナの「売られた花嫁」です。
これまで全曲、抜粋を含め7種の録音を聞く機会がありましたが、その中で原語で歌われたものは2種にすぎず、英語が2種、残りの3種はドイツ語によるものです。
そのドイツ語訳はすべてマックス・カルベック(1850-1921)によるものであり、19世紀後半から、これがヨーロッパのオペラ・ハウスのスタンダード・レパートリーとなったそうです。
今夜聞いたホルライザー盤は、昨年に復刻されたようです。これまで聞いてきたドイツ語による録音にあって、より濃い浪漫性が漂う演奏と言えるでしょうか。ブッファらしい軽快な躍動感は感じにくいものの、土に根ざした民族的な色彩を忍ばせている感もあります。
この録音はもともと抜粋として制作されたものと思いますが、キャラクター・テノールとして際立つヴェンツェルが歌わない場面ばかりを集めています。
このオトナになりきれないマザコン男は、捉えようによっては(描き方によっては)、"差別"になりかねないことが多いことは既に語られているところですが、ブッファでありながら、そのような問題を提起してしまうのは、やはり、このオペラがいかに民衆に根ざしたオペラであるかを物語っているような気がします。
.
2009/Sep
06
Sunday
00:10
Comment(-)
リヒャルト・シュトラウス(1864-1949)
楽劇「エレクトラ」より
1: エレクトラのモノローグ
2: エレクトラとオレストの再会
3: フィナーレ
エレクトラ: インゲ・ボルク
オレスト: パウル・シェッフラー
クリソテミス: フランセス・イーンド
シカゴ・リリック劇場合唱団
シカゴ交響楽団
指揮: フリッツ・ライナー
録音: 1956年
(40:55)
今夜はR. シュトラウスの「エレクトラ」です。
前回聞いた「運命の力」はストーリーは陰惨であるものの、音楽は一つの悲劇として見事にとどまっていました。それに対して、「エレクトラ」はもっと人間の根に潜む性を抉った古典ですが、音楽はかなり過激なものとなっています。
しかし、「エレクトラ」はベルクの「ヴォツェック」のような問題提起をして幕となるものではなく、「ニーベルングの指環」と同様に、崩壊によって生じるカタルシスを得られるものとなっています。
題名役のボルクは、ベーム指揮による全曲盤でさらに素晴らしい歌唱を聞かせてくれますが、シェッフラーの落ち着いた深みとコクがあるオレストは同役の筆頭に挙げたいくらいです。また、ライナー率いるシカゴ交響楽団の充実ぶりも特筆すべきでしょう。
なお、シェッフラーはドン・アルフォンソとしてもお気に入りの歌手です。
深夜便48 モーツァルト 「コシ・ファン・トゥッテ」 ベーム
ドン・アルフォンソとオレストではだいぶ役どころが異なりますが、シェッフラーの歌唱はそれを描き分けて妙と思いました。
この録音は、かつて聞いた「サロメ」とカップリングとなっており、R. シュトラウスの過激なオペラのエッセンスを1枚のディスクで堪能できます。
深夜便40 R. シュトラウス 「サロメ」 ライナー
ところで、4日後の9月8日はR. シュトラウスの命日となりますが、その日は他の作曲家を優先すべく、先にこれを聞くことにしました。
.
2009/Sep
04
Friday
22:00
Comment(-)
ヴェルディ(1813-1901)
歌劇「運命の力」ハイライツ
レオノーラ: レナータ・テバルディ
アルヴァーロ: マリオ・デル・モナコ
カルロ: エットーレ・バスティアニーニ
プレツィオジッラ: ジュリエッタ・シミオナート
グァルディアーノ: チェザーレ・シェピ
メリトーネ: フェルナンド・コレナ
軍医: エラルド・コーダ
ローマ・サンタ・チェチーリア音楽院管弦楽団&合唱団
指揮: フランチェスコ・モリナーリ・プラデッリ
録音: 1955年
(58:25)
今夜はヴェルディの「運命の力」です。
このオペラは「仮面舞踏会」に続く作品となり、1862年にサンクトペテルブルクのマリインスキー劇場で初演されています。これが所謂「原典版」であり、改訂版は7年後の1869年にミラノ・スカラ座で上演されました。
原典版では短い前奏曲であったものが、改訂版で「ナブッコ」、「シチリアの晩鐘」とならぶ有名な序曲に差し替えられています。
原典版では主だった登場人物がすべて死ぬという設定でした。拳銃の暴発による事故死、決闘による死、殺人、そして自殺と陰惨なものばかりですが、改訂版では、最後のアルヴァーロの自殺シーンがカットされました。
聖職者が自殺するということが問題視されたためと言われています。しかし、かつての恋人であるレオノーラが、その死に際して「先にまいります、アルヴァーロ様」と言っていますし、聖職者として決闘の末にレオノーラの実兄を殺めたからには、必然的に改訂版でもアルヴァーロの余命もそう長くは無いことを暗示しています。
きわめて無情なストーリーではありますが、音楽は素晴らしいのです。改訂版は「ドン・カルロス」を作曲した後に書かれていることもあり、ヴェルディの中期の総決算的な充実度があります。(これらの後に書かれたオペラは、「アイーダ」、「オテロ」、そして「ファルスタッフ」。)
なお、この抜粋盤でクレジットの無い諸役は、以下のとおりのようです。
カラトラーヴァ侯爵: シルヴィオ・マイオニカ
クッラ: ガブリエッラ・カルトゥラン
トラブーコ: ピエロ・ディ・パルマ
.
2009/Sep
02
Wednesday
19:00
Comment(-)
プッチーニ(1858-1924)
歌劇「ラ・ボエーム」全曲
ミミ: レナータ・テバルディ
ムゼッタ: ヒルデ・ギューデン
ロドルフォ: ジャチント・プランデッリ
マルチェロ: ジョヴァンニ・インギッレリ
ショナール: フェルナンド・コレナ
コルリーネ: ラファエル・アリエ
パルピニョール: ピエロ・デ・パルマ
ベノア / アルチンドロ: メルキオーレ・ルイーゼ
税関の役人: イルデブランド・サンタフェ
サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団&合唱団
指揮: アルベルト・エレーデ
録音: 1951年
(52:12/52:39)
今夜はプッチーニの「ラ・ボエーム」です。
モーツァルト、ロッシーニ、ワーグナーによるとても好きなオペラを年代順に聞いてきましたが、その締めくくりはプッチーニです。今回はヴェルディを割愛していますが、それは今月初めに「マクベス」を聞いたためです。
「トリスタン」では1950年代初頭の歴史的な演奏を聞きましたので、「ラ・ボエーム」もその前年に収録されたエレーデ盤としました。音質は古めかしい感は否めませんが、モノラル録音とは思えないほど豊かなサウンドとなっているのは、演奏の質によっていることと思います。
ここでのミミはレナータ・テバルディですが、後年の録音よりも若々しさが魅力となっています。
深夜便35 プッチーニ 「ラ・ボエーム」 セラフィン
セラフィン盤では前半2幕がいささか貫禄がありすぎる感もありましたが、このエレーデ盤では可憐さも兼ね備えています。
そして、それ以上にここでの聞きものは、ギューデンの愛らしいムゼッタでしょう。ギューデンとなると、往年のモーツァルト&R. シュトラウス歌手といったイメージがありますが、独特の厭味のない"軽み"が魅力的です。こ「オペラ深夜便」では、かつて、ゾフィーをギューデンで聞いています。
深夜便47 R. シュトラウス 「ばらの騎士」 ヴァルヴィーゾ
.
2009/Aug
30
Sunday
19:00
Comment(-)
ワーグナー(1813-1883)
楽劇「トリスタンとイゾルデ」第2幕
イゾルデ: キルステン・フラグスタート
ブランゲーネ: ブランシェ・シーボム
トリスタン: ルートヴィヒ・ズートハウス
クルヴェナール: D. F. ディースカウ
メロート: エドガー・エヴァンス
マルケ王: ヨーゼフ・グラインドル
フィルハーモニア管弦楽団
指揮: ヴィルヘルム・フルトヴェングラー
録音: 1952年
(49:35/37:24)
今夜はワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」第2幕です。
この曲の第2幕は、あまりにふたりの題名役に負担が大きすぎるためでしょうか、第2場の一部がカットされることがあります。この部分は、所謂「昼の対話」と呼ばれる場面です。
この部分をカットすると、いささかイゾルデの歌詞の流れに無理が生じるのですが、音楽的にはあまり溝が生じません。これがそのカットを広めた理由の一つになっているかもしれません。古い年代の録音で聞くと、この場面がカットされていることが多く、如何にこれが一般化していたかを窺うことができます。
「昼の対話」は、トリスタンとイゾルデがすべてが白日の下となる昼の束縛からの逃避を願い、夜を賛美する前後と対照をなす場面と位置づけることが可能でしょう。そこにワーグナーが作曲した音楽は、かなり激情をともなっており、いったんこの魅力にとり憑かれてしまうと、やはりカットには馴染めなくなってしまいます。
古い年代の録音では、歌手がすばらしいことが多く、それだけに、そのカットがあることにとても残念に思うことがあります。今夜聞いたフルトヴェングラー盤は、モノラル時代の録音ではありますが、「昼の対話」のカットはありません。
とても聞き応えのある名演と思いますが、件の「昼の対話」については、落ち着き払っている感が無きにしもあらずでした。
2009/Aug
28
Friday
21:00
Comment(-)

